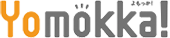Sagasokka!活用事例
相模原市立田名小学校
【1年生/国語】
1年生から『Sagassoka!』。「自分でできた!」小さな成功体験が調べる活力に
夏の生き物を調べたり、絵を描くための資料を探したり、これまで小学1年生のクラスで『Sagasokka!』を活用してきた、相模原市立田名小学校の根岸真由先生。今回は、国語「しらせたいな、見せたいな」の授業の様子を伺いました。

・内容/用途 国語 しらせたいな、見せたいな ・利用開始 2022年4月 Sagasokka!
興味のある動物を『Sagasokka!』で検索。本とは違った良さも
工夫した点は、資料として学校図書館で借りてきた本と『Sagasokka!』の2つを用意し、こどもたちの選択肢を広げたところです。1年生が『Sagasokka!』の項目本文を読むのはハードルが高いかもしれませんが、画像・資料は、こどもたちの活動を広げる手立てになります。前の単元で、画像を拡大し細かなところまで観察するこどももいたため、今回の単元でも『Sagasokka!』を活用することに決めました。


『Sagasokka!』で検索できる動物の画像の一部。「大きく表示」を押した後、さらに拡大してじっくり観察していた
●家の人に知らせたい動物(今回は対象を「動物」に絞った)を選ぶ
●『Sagasokka!』や本に載っている画像、イラストを見て観察し、文章を書くためのメモ(絵や言葉で記録)を作成する

『Sagasokka!』と本を使って「アオウミガメ」をじっくり観察。
「大まかな形を本で、細かな模様は『Sagasokka!』の画像で調べるとわかりやすい」と使い分けることにしたのだそう

『Sagasokka!』に掲載されている動画を視聴して気に入ったタイミングで停止して絵を描いたり、動画から得た情報(足が速いなど)をメモに書いたりする姿が見られた
こどもたちが初めて『Sagasokka!』を開くとき、操作練習に1時間ほど使いましたが、今ではスムーズに使っています。2~3度検索したあたりからこどもたち同士で教え合う姿も見られるようになり、一人でも調べたいことを調べられるようになりました。自分で調べられるということが、とてもうれしくて、楽しいようです。
また、興味のある画像にたどり着いたときなど「自分でできた!」と、小さな成功体験が得られ、この小さな成功体験は「もっと調べたい」という一歩に繋がるのではと感じています。自分で題材を探して、決めて、自分で調べる。低学年も『Sagasokka!』を使うことで、多くの子が手軽に「調べたいことを調べる」ための力の素地を身に付けることができるように思います。
検索といってもWeb検索だと多くの情報があり、まだ情報リテラシーが十分でない年齢だと判断が難しく誤った情報や学習の意図から逸れた情報に出合う可能性もありますが、『Sagasokka!』はある程度情報が限定されており、学習にフォーカスしているので、低学年からでも授業に取り入れやすいです。

授業の終盤、「家でも続きをやりたい!」と声が上がった
こどもたちの成果物(メモや、メモをもとに書いた文章)